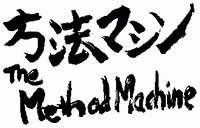 | method-machine.com 最新情報 | 概要 | メンバー募集 | 練習日程 | メルマガ | 記録 | 公開講座 |マシンの花道 |方法 | お問合せ |
メルマガ2006年7月号
◎◎◎方法マシンからのおたより 7月号◎◎◎ ◎目次◎ 『またりさま全公案連続演奏会』特集!! ○『またりさま全公案連続演奏会』にむけてー公演統括の言葉 by篠田昌伸 ○特別寄稿ーまたりさま作曲者の言葉 by三輪眞弘 ○またりさま判定機「matari2005」について byさかいれいしう ○公演案内○『またりさま全公案連続演奏会』 ○report○トム・ジョンソンコンサート by池田拓実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ◎『またりさま全公案連続演奏会』にむけてー公演統括の言葉◎ 我々方法マシンは、過去2回の公演において、様々な方法芸術作品をバラエティ の富んだ形でリアライズして来た。その中で『またりさま』は、「演算するからだ 展」においてはその儀式性を強調する形で、「第一回定期公演」においては、観衆 にその仕組みをわかりやすく伝える為に、マシンの訓練の様子を見せるといった形 でリアライズを行った。 しかしそれらは、『またりさま』を”紹介する”という段階に留まっていたのか もしれない。 実質3回目の公演を行なうにあたって、我々は様々な方法芸術作品を取り上げる ことをせず、『またりさま』のみを完全な形で見せる、という道を選んだ。それは、 『またりさま』を高速で行なうということが方法マシンの設立の理由のひとつであ ったこともあるが、様々な方法芸術作品と戯れることによって、マシンが娯楽性に 下りていくことの危機を感じたためでもある。また『またりさま』は、最も方法マ シンの趣意書に即したものでもある。『またりさま』を訓練することは、方法マシ ンがマシンとしての性能をあげる現時点での最良の方策であり、それが完璧になさ れることによって今後の他の作品のリアライズにも還元されるだろう、という信念 のもとに、今回の公演をおこなうものである。 ほぼ半年の間、マシンは『またりさま』の訓練のみに集中し、その中で様々な練習 方法が編みだされ、また練習ソフトも進化していった。そして、本公演では、マシ ン内のオーディションを経て選出された精鋭メンバー8人によって、完全なる『ま たりさま』を実現させる。くり返して言うが、『またりさま』は方法マシンの真髄 であり原点でもある。今回の公演を見ずして方法マシンを見たことにはならない、 と言っても過言ではないだろう。 (文:篠田昌伸) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ◎特別寄稿ーまたりさま作曲者の言葉 2002年4月14日、第二回方法芸術祭(阿佐ヶ谷ギャラリー倉庫)で発表された 「またりさま」は今に至る私の作曲活動に決定的な影響を与えた作品だった。機関 誌「方法」第15号の「身体を合成する」で述懐したように、「新しい音楽(作曲) を考えるには新しい身体を考えるしかない!」・・当時私はそう思いつめていた。 その切迫した気持ちと夢は後に「逆シミュレーション音楽」というアイデアを生み、 また他ならぬ方法マシンというパフォーマンス・グループ結成へとつながって行っ た。方法マシン結成時の趣意書最後の一節、「『方法マシン』は文化的洗練の絶対 ゼロ地点からの出発も辞さず、地上に新たなる方法芸術を顕現させることを目的と する。」こそ、この私の思いつめた気持ちの核心部分である。それは、私にとって 現代の音楽を取り巻くあらゆる状況、作曲家、演奏家、聴衆という役割やコンサー トという社会システム、オーディオ・データ或いは商品としての「音楽」などを根 底から批判し、未来の音楽を構想する試みである。 「またりさま」は数学的なシステムと創作されたお伽噺に基づく、鈴とカスタネ ットだけで演奏される作品である。単純な規則を理解すれば子供でもできるはずだ。 しかしそれは古今東西のあらゆる芸能や儀式と同様に「神が宿る」瞬間を生み出す 装置でもある。作品には何の神秘も介入する余地は残されていないにも拘わらず、 である。ただ、そのためには「またりさま」を「本当に」演奏しなくてはならない。 それは単に「やってみる」こととは本質的に異なる次元のことである。最高速で演 奏される「またりさま」はそれを見守る人々を驚かせたり感心させたりすることが 目的ではない。パフォーマー達がそれを「本当に」演奏できる身体を現実世界の中 で獲得することこそが肝心なのである。それが実現した時に初めて現代社会の中で この新しい作品が存在したと言い切ることができるのだ。それは「ジャズにXXと いう曲がある」、「清元のXXという曲」と表現されることと同じ文脈において 「またりさまという作品」、即ち技芸がこの地上に出現したことを意味するからで ある。 今回の公演に向けて、時々刻々変化するパフォーマーの状態を記憶し反射的に楽 器を操るための練習メソードや、63周で繰り返すループを自動的にカウントする 「鬼送り」と名付けられた技法など、練習過程の中で実に多くの発見があり工夫が なされた。それらが先に述べた「文化的洗練の絶対ゼロ地点からの出発も辞さず」 の意味である。 (文:三輪眞弘) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ◎またりさま判定機「matari2005」について MTSS2005「またりさまソリューションサービスプロジェクト」概要 次回の演奏会をスムーズにかつ強力にバックアップするための演奏判定装置「m atari2005」の制作と運用を目標とし「またりさまソリューションサービスプロジ ェクト」が結成された。元・ハード部のさかい、森下が発起人となり、元ソフト部 のポイ野、イケdが参入。その後、新メンバー森本が参入、現在5人で構成されて いる。 奏者のスズとカスタネットにセンサーをとりつけ、演奏された音をコンピュータ でデータ化して記録、演奏が正しく行われたかの判定を行う仕組みである。・・そ んなにも方法マシンとマシンは仲良しなのか?という声が聞こえてきそうだ。イエ ス、そのとおり!・・と、自問自答をするところにも実はポイントがあるのかもし れない。コンピュータに計算させた方が遥かに速く簡単なはずの「またりさま」を マシンは数ヶ月をかけて訓練しているが、その完成度を高めるためにコンピュータ を利用しているわけだ。 もしかしたら我々は、『逆シミュレーションのシミュレーションをせよ』という 自己言及的なメッセージをコンピュータから受け取って突き動かされているのかも しれない。私たちはどこからどこまでがマシンなのだろうか? ただいまぐんぐんと制作中につき、演奏会での登場をお楽しみに。 (文:さかいれいしう) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ◎第21回<東京の夏>音楽祭2005関連公演 方法マシン特別仕様「またりさま全公案連続演奏会」 方法マシンの次回公演は、三輪眞弘(2004年芥川作曲賞受賞)の問題作に真っ向 から挑む!数学的に解明された「またりさま」の全演奏パターン(公案)を一挙連 続演奏。究極の超高速人力アルゴリズム体験をあなたに! (演奏時間最短10分。当日のマシンの性能により変更があります) 終演後のアフタートークに、中沢新一氏、沼野雄司氏出演決定。「架空の伝統芸能」 である『またりさま』を現代の論客が斬るや如何に? 日 程:2005年7月31日(日)開場13:30 開演14:00 終演14:10 (終演後アフタートークがあります) 会 場:門仲天井ホール (東京都江東区門前仲町1-20-3-8F tel03-3641-8275) http://www5f.biglobe.ne.jp/〜monten/ 監 修:三輪眞弘 演 奏:方法マシン アフタートーク出演:中沢新一、沼野雄司、三輪眞弘、鶴見幸代、足立智美(司会) 協 賛:アサヒビール 主 催:方法マシン 詳細は http://www.method-machine.com/ チケット:前売1500円 当日2000円(全席自由) チケット予約:ticket@method-machine.comへ、 件名を「またりさまチケット予約」として以下を記入の上お送りください。 ・お名前 ・ご住所 ・電話番号 ・チケット枚数 代金支払、受取方法について、折り返しご連絡いたします。 お問い合わせ:ticket@method-machine.com tel&fax 03-3921-4309(ナヤ・コレクティブ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ◎report◎トム・ジョンソンコンサート 6月21日、公園通りクラシックス(渋谷)にて「トム・ジョンソン来日!コンサー ト/講演〜自作自演によるピアノ曲セレクションを中心に」が開催された。ジョン ソン氏は1939年コロラドに生まれ、モートン・フェルドマンに師事、1987年まで に算術的な操作による作曲のスタイルが完成し今日に至る。今回は1965年以来40 年ぶりの来日となった。公演は、昨年神奈川で日本初演を行なった方法マシンによ るCounting Duets(1982)で開幕、今 回は鶴見、さかい、深澤、安野の四人のメン バーにより演奏された。その後ジョンソン氏自身のパフォーマンスおよびピアノ演 奏により、Counting Languages(1982、抜粋)、Counting Keys(1982-89)、Pa scal's Triangle(1988)、Tilework for Piano(2002)、Kirkman's Ladies(2005) が演奏された。続く講演でジョンソン氏は、ケージの引用に始まる数々の例から無 為の音について説いた。またある時は、振り子を取り出して振り子の周期がその長 さの平方根に比例するという法則を示し、自然界における法則性、数とシンメトリ の興味深さについて説き、自らの創作と関連付けた。 (文:池田拓実) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ メールマガジン配信の解除、メールアドレスの変更及びバックナンバーの閲覧は 下記URLを御覧下さい。 http://method-machine.com/otayori/ 本誌は、他者への転送は自由ですが、改竄や盗用は禁止します。 |
メルマガバックナンバーバックナンバー一覧 |