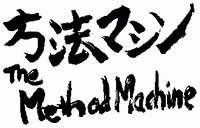 | method-machine.com 最新情報 | 概要 | メンバー募集 | 練習日程 | メルマガ | 記録 | 公開講座 |マシンの花道 |方法 | お問合せ |
メルマガ2005年8月号
◎◎◎方法マシンからのおたより 8月号◎◎◎ ※今月号はメール送信ソフトの不具合により、編集長深澤のパソコンからBCCで お送りしています。 ◎目次◎ ○ワークショップのお知らせ○ ○report○『またりさま全公案連続演奏会』 深澤友晴 ○今月の方法作品 Tom Johnson『Counting Duet』 池田拓美 ○写真 『またりさま全公案連続演奏会』より 撮影:大久保紀代子 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ◎緊急決定!公開合同練習『またりさま体験』 日時: 2005年8月7日(日)15:30-16:30 場所: 高円寺北会議室 洋室2 (高円寺駅北口から徒歩5分、地図は下記URLで御覧下さい) http://www.tpa.jp/info/map_1.gif 先月の『またりさま全公案連続演奏会』、ご来場のみなさまありがとうございました。 現在、方法マシンでは、大好評の『またりさま』についてワークショップを計画中で すが、次回の合同練習では『またりさま体験』と題して、候補メンバーの訓練及び自 由参加の簡易的なワークショップを行うことになりました。『またりさま』実演に興 味のある方なら、どなたでも参加可能です。入場料、予約は不要です。振るってご参 加ください。 (文:鶴見幸代) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ◎report◎『またりさま全公案連続演奏会』 昨日07月31日、方法マシン3度目の公演となる、『またりさま全公案連続演奏会』 が行われた。方法マシンはこの半年の間、この公演のために練習を繰り返してきた と言っても過言ではない。 開始時間が近づくと8人の演奏者がしずしずと一列になって登場。円を描くように 中央の平台の上に座り、それぞれが前に座る者のうなじに項隠しをかける(前に座 る異性の項が見えることは雑念を生じさせる元となるため)。そして演奏者たちは 右手に鈴、左手にカスタネットをつける。すると、MCの安野太郎が登場し、今回 の公演についての簡単な解説を行う。代表の鶴見による「またりー、はいっ」のか け声とともに、「空」、「双子兄」、「双子弟」、「対称形姉」、「対称形妹」、 「星合の公案」という6つの公案(初期値)が、順に演奏されていく。 当初の目的の一つであった「一度も間違えない」ということについては結局数度の 間違いがあり達成できなかったが、「『またりさま』を高速で行う」というもうひ とつの目的は、十分に達成できていたと思う。 演奏後は宗教学者中沢新一氏、沼野雄司氏を迎え、『またりさま』作者の三輪眞弘 氏、方法マシン顧問の足立智美氏、そして方法マシンから代表の鶴見幸代が参加し てアフタートークが行われた。音楽と宗教との結びつき等、『またりさま』に関連 する興味深い話題が話し合われた。 (文:深澤友晴) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ◎今月の方法作品 Tom Johnson『Counting Duet』 Tom Johnsonの作品、Counting Duets(1982)は五曲から成る。打楽器譜のよう な楽譜には音符ではなく数字が記されており(※1)、二名の奏者は数詞を発声する。 用いられる数列は全て1ずつ増えたり減ったりするもので、それが曲ごとに入れ子 や交差などの様々な方法で組み合わされる。各曲の構造は単純かつ概ね一貫してお り、恐らく足し算と引き算と九九ができる人なら誰でも演奏でき、また聴くことで 容易に構造を理解し楽しむことが出来る。従ってプログラムを書いてコンピュータ に実行させることも容易である。と思われた。そこで昨年の神奈川公演ではCounti ng Duetsのシミュレーションプログラムを展示することになったが(※2)、 配列(※3)を用いずに、簡単な演算子の組み合わせだけで実現するという試みは、 しかし時間切れとなり失敗した。つまり第IV曲と第V曲を除いては(※4)、拍数を 数えて随時計算規則を切り替えるなどの「例外処理」がどうしても必要になったの だった。詳しい説明は難しくなるが、例えて言うならその原因のひとつは、曲中に 「0」が出てこないことにある。あるいはやはり、私の不手際であるかも知れない。 先日6月21日に、Tom Johnsonが来日しコンサートが催された際に(※5)、この 「例外処理」について本人に尋ねるかとも思ったが、あまり意味がないように思わ れたのでやめた。当日、再度Counting Duetsを演奏したマシンメンバーによれば、 作曲者からはリズムやアクセントなどの音楽的要素について様々な指導があったと 言う。また作曲者自身のパフォーマンスによるCounting Languages(1982)が独特 のグルーヴ感を伴っていたことも、非常に興味深いことだった。思うに、作曲家が 意図しているところとは「数えることで音楽ができる」ということであってその逆 ではない。 (文:池田拓美) ・トム・ジョンソン氏のHPです。 http://www.tom.johnson.org/ ※1つまり楽譜には数列の生成規則が書かれているのではない。 ※2 PureData(http://www-crca.ucsd.edu/~msp/software.html)を使用。 ※3 予め用意した数列。Counting Duetsでは楽譜に等しい。 ※4 この二曲については大成功だった。 ※5「方法マシンからのおたより・7月号」にレポートを掲載。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ メールマガジン配信の解除、メールアドレスの変更及びバックナンバーの閲覧は 下記URLを御覧下さい。 http://method-machine.com/otayori/ 本誌は、他者への転送は自由ですが、改竄や盗用は禁止します。 |
メルマガバックナンバーバックナンバー一覧 |