第四回「総合芸術の対立概念としてのインターメディア芸術」
2005年6月5日(日)13時30分より
下目黒住区センター 2階 下目黒老人いこいの家にて
|
講師:足立智美 総合芸術批判は方法主義の重要な眼目のひとつでした。あらためてモダニズムの立場から総合芸術を定義/批判するとともに、総合芸術の対立概念でありモダニズムを相対化する要素をあわせもつインターメディアの概念を詩、音楽、ダンスなどの領域における実例とともに検証します。 今回の講師は音楽家の足立智美氏です。インターメディア芸術とマルチメディア芸術についての概略と、氏が方法主義に参加し、脱退に至るまでの経緯が語られました。 絵画の世界では1960年代にモダニズムの議論がわき起こりました。グリンバーグは文学的テーマや絵具の盛り上がりの三次元性を排除し「絵画は色彩の平面に還元されるべき」という理論を提出しました。ドナルド・ジャッドはそれを起点にモダニズム絵画を突き詰めたものとしてミニマルな立体作品を作成しましたが、マイケル・フリードはそのような作品はモダニズムの理論をリテラルに実現しただけのもので「その経験こそが『演劇的』である」としてモダニズムの立場から批判しました。この場合『演劇的』とはメディアの混合を指します。しかしフリードの見解を超えてジャッドの作品のはらむ『演劇性』はメディアの相関をめぐる別の可能性をはらんでいます。モダニズムの還元主義に並行する概念として60年代半ばにディック・ヒギンズが用いた「インターメディア」があります。メディアとメディアの間にあるものを意味し、還元によって分野の決定が不可能となるものです。インターメディアはモダニズムからミニマル・アートに転化していくプロセスを反モダニズムの立場から説明する位置にあります。インターメディア、あるいはより新しい概念としてのパラ・メディアの作品として、詩とも絵画とも言える新国誠一の視覚詩、ダンスの身振りか絵画か判別できない振付家のトリシャ・ブラウンの作品、漢字を象形文字から画像へと移し変えCDに焼き付け、音楽用CDプレイヤーで再生する刀根康尚の作品などが例として挙げられます。 オペラのような総合芸術は、音楽、美術、舞踊、文学など異分野の「組み合わせ」のマルチメディア芸術です。足立氏が方法主義に参加した際の関心のひとつは、新しい還元主義による方法主義が、他のジャンルとのコラボレーションをマルチメディアに依らず実現できることにありました。方法主義は芸術を「方法」に還元します。例えばある数列を用いるという「方法」であれば、音楽にも絵画にも文学にも適用することが可能なのです。 インターメディア芸術の特質は、理論が事後的に現れ、作家の理論付けが作品に表れるか否かは、常に未知数なことです。方法主義者として一時活動していた足立氏は「方法主義が芸術の理論的権威付けを目指す」点で離れることになりました。氏は、今後も音楽を懐疑し解体するために、音楽家を名乗って活動し続けると語りました。 |
  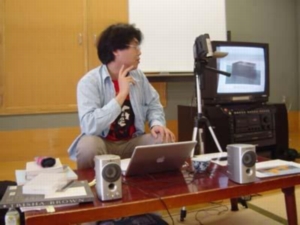
|