第一回「逆シミュレーション音楽、或いは方法音楽の未来」
2005年2月6日(日)13時30分より
目黒区青少年プラザ 会議室にて
|
講師:三輪眞弘 方法主義者としての活動の中から突如出現した、三輪の提唱する新しい作曲技法「逆シミュレーション音楽」。それはなぜ考えられ、また生み出されねばならなかったのか?音楽を取り巻く現代の状況と三輪の活動の軌跡を重ね合わせながら様々な実例をもとに芸術表現の未来を考える。 今回の講師の三輪眞弘氏はコンピュータを用いた作曲で知られる作曲家です。今回の講座では、三輪氏の提唱する新しい作曲技法「逆シミュレーション音楽」を主軸として、テクノロジーと芸術との関わりについて述べられました。 コンピュータを用いた芸術は既に長い歴史を持っています。コンピュータを用いた実験的な作曲は、コンピュータの歴史の最初期から行なわれていたもので、コンピュータ・テクノロジーが芸術の可能性を拡張するという期待も、その時から存在していました。 一方で、私たちの生きる現代のコンピュータ・テクノロジーは、既にWWWや世界市場を形成するものでもあり、軍事力そのものでもあります。ある音響技術は、そもそもは潜水艦のソナーのために開発されたものでした。このようなところから「テクノロジーと引き換えに人間が差し出してしまったものが何であったか」について考えることが、テクノロジーを用いた芸術の役割ではないかと三輪氏は問います。 方法マシンのレパートリーでもある「またりさま」は「逆シミュレーション音楽」のひとつです。「逆シミュレーション音楽」とは、ある一定の計算の繰り返しを予めコンピュータで検討し、その計算を人間が同じように繰り返す行為に移し変えたものです。コンピュータによるシミュレーションを逆に人間がシミュレートする、この技法は、演奏者が正確な行為を無心に繰り返すことを求めます。儀式のような様相を帯び、架空の民族や文化についての物語(由来)が伴う逆シミュレーション音楽を通して、音楽とテクノロジーの関係が深く解説される時間となりました。 講座では「またりさま」の紹介のほか、芥川作曲賞受賞作の管弦楽作品「村松ギヤ・エンジンによるボレロ」、「ハープのための『すべての時間』」の演奏記録が示されました。講義後は、作曲技法に関わる熱心な質問が受講生から向けられていました。 |
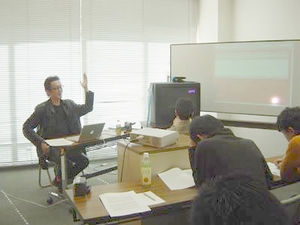   
|